おひとりさまとしてこれからの人生を見据えたとき、お墓の管理や継承の問題は避けて通れない大切なテーマです。
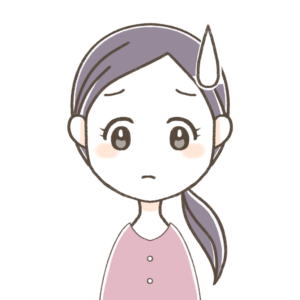
代々続く家族のお墓がある場合、子どものいないおひとりさまは、
自分が亡くなった後のお墓の管理についても考えておかなくてはならないですよね…
今回の記事では、終活における墓じまいという視点から、これからの生活を安心して過ごすために知っておきたい情報や必要な手順、注意点などをわかりやすく解説します。
自分らしい最後を迎えるために、今からできることを一緒に考えていきましょう。
終活における墓じまいとは

「墓じまい」とは、長年管理してきたお墓を撤去し、墓地を元の替地に戻して管理者に返還する手続きを指します。
これまでは代々継承されるのが常識だったお墓ですが、近年、少子化や核家族化の進行により、墓を継ぐ人が見つからない事態が増えてきています。その結果、墓を維持し続けることが難しくなり、管理費や修繕費などの負担が大きくのしかかっているのが現状です。
このような背景から、未来への備えとして墓じまいを検討する人が増えています。墓じまいは、終活を考える上でとても大切なプロセスです。
しないとどうなる?墓じまいが重要な理由
おひとりさまの場合、継承者がいないことは大きな問題です。放置しておくと無縁墓と呼ばれる状態になり、結局は自治体や管理者によって撤去されてしまいます。最終的に他の無縁墓の遺骨と一緒に合葬されます。そのため、お墓を継ぐ兄弟などがいない場合は、生きているうちにしっかりとした手続きをしておくことが大切です。
自分自身で整理をすることで、後の誤解やトラブルを防ぐことができ、心安らかに人生の最後を迎える準備ができます。結果として自分らしい終活を実現するための第一歩となります。
墓じまいの手順と注意点
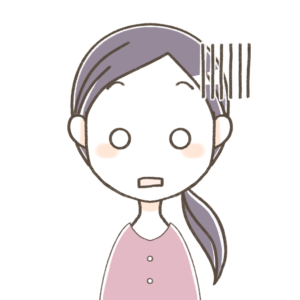
墓じまいってなんだか大変そう…
「墓じまい」と一言で言っても、遺骨が入っているため、簡単にお墓を撤去してお引越しという訳にはいきません。お墓を移動するためには、行政手続きやお墓の解体業者、新しい受け入れ先を検討する必要があります。最近では、墓じまいをトータルにサポートしてくれるの業者に任せることができるので安心です。
ここからは、墓じまいの流れや費用について確認しておきましょう。
1.親族で話し合う
墓じまいを検討する前に、最初に必ず行うべきことは親族との話し合いです。先祖代々のお墓には、身近な家族だけでなくあまり会ったことのない遠縁の親戚が埋葬されているケースもあります。
お墓参りを習慣化していた親戚からすれば、今まで手を合わせに行っていたお墓がなくなることに抵抗を感じる方もいるでしょう。また、継承を希望する方がいるかもしれません。
お墓についての考えは人それぞれ違います。トラブルを避けるためにもしっかり話し合い、親族全員の了承を得ておくことが大切です。思いを共有することで、精神的な負担も軽減され、スムーズに手続きを進めることができます。
2.新しい供養方法を決める
親族との話し合いの際、同時進行で新しい供養方法を相談しておく必要があります。墓じまいには「改葬許可証」が必要であり、新しい供養が決まっていないと改葬許可証を取得できません。
墓じまいをすることに了承を得たら、新しい供養方法を最終決定しましょう。おひとりさまは、跡継ぎがいないという理由で墓じまいをするケースが多いので永代供養できる方法を検討するとよいでしょう。
3.現在の墓地管理者に相談する
前述のとおり、墓じまいの手続きの際には現在の墓地管理者に埋葬証明書を発行してもらう必要があります。霊園などであれば管理事務所に伝えましょう。
寺院の場合は檀家をやめることになるため、寺院に墓じまいをしなくてはいけない理由や感謝の気持ちを伝え丁寧に説明することが大切です。遺骨を別の霊園や寺院に移す場合は檀家関係を解消する「離檀」にあたります。
寺院にとって墓じまいは、檀家からのお布施や使用料などの収入がなくなってしまうことにもつながります。離檀の際には高額な離檀料がかかる場合もあるので気をつけてください。
4.墓じまいを依頼する業者を決める
墓じまいには墓石の解体・撤去が必要です。一般的には石材店に依頼しますが、施設によっては業者が指定されているため必ず確認しておきます。
墓じまいにかかる費用は決して安いものではありません。自分で業者を選定する場合、工事の費用や作業内容は業者によって異なるため、必ず複数の業者に見積もりを依頼し、比較検討しましょう。
契約内容に不明点がないかしっかり確認し、追加料金が発生しないか注意深くチェックすることも大切です。できれば現地立会いのうえで打ち合わせを行うとより安心です。
>>全国対応!お寺とのトラブル・離檀のことならお任せください【わたしたちの墓じまい】公式サイトをチェックしてみる
5.行政手続きをする
お墓をお引越しするには、自治体で手続きをして「改葬許可証」を発行してもらう必要があります。
改葬許可証を入手するためには以下の書類が必要です。
改葬許可証を発行してもらったら墓じまいの手続きは完了です。
6.閉眼供養をする
仏教の方は、お墓からお骨を出す時に「閉眼供養」を行います。閉眼供養とは、お墓に宿っている仏様の魂を抜き取るための儀式で、墓前で僧侶に読経してもらいます。
7.お墓を解体する
行政手続きと閉眼供養が済んだら解体・撤去工事の開始が可能です。墓石を撤去し遺骨を取り出して更地に戻したら、墓地をお墓の管理者へ返還します。
新しい受け入れ先で遺骨を供養しましょう。
墓じまいにかかる手続き・費用

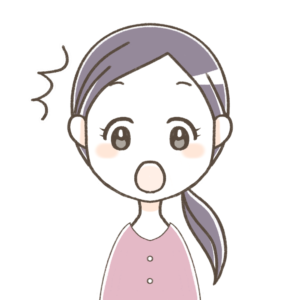
墓じまいの流れはわかったけれど費用が高そう……
墓じまいの流れを確認しただけでも費用がたくさんかかりそうですよね。
ここからは費用相場をみていきましょう。
お墓の解体にかかる費用相場
お墓の解体にかかる費用相場は以下の通りです。
お墓の撤去費用は、お墓の大きさや広さにより費用は変わります。
また、お寺にお墓があった場合は離檀料が必要になりますが、離檀料にはとくに決まったルールはありません。今までの感謝の気持ちとして納める慣習になっています。
行政手続きにかかる費用相場
「改葬許可証」を発行してもらうために手数料がかかる場合があります。
手数料は自治体によって異なりますが、無料のところもあり大きな金額にはならないでしょう。
新しい供養先にかかる費用相場
墓じまいをした後は、新しい供養先によって費用が異なります。
墓じまい同様、遺骨の供養の方法は大切な選択です。
お墓を継ぐ人がいないという理由で墓じまいをしたのであれば、新しい形式を取り入れて供養しなくてはいけません。どのように遺骨を供養し、ご先祖さまと向き合っていくかを考えることが大切です。
まるっと墓じまい代行業者に頼むのがラク
さまざまな手続きのトラブルや費用について心配な方は、墓じまいの代行サービスを活用するのがおすすめです。【わたしたちの墓じまい】なら、お寺との交渉や行政手続きから供養まで、終活全般のサポートをまるっと依頼できます。
他社と比べてもお値打ち価格かつ、終活支援全般をきめ細やかに対応してもらえます。
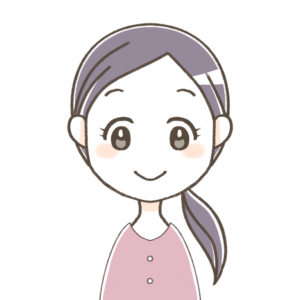
創業18年で日本全国で施工実績があるのも安心ですね!
墓じまいはポジティブな選択!これからを自由に生きるために

この記事ではおひとりさまの墓じまいについて解説しました。
墓じまいは、自分の生き方や価値観を映し出し、自分らしい終活を実現するための前向きな選択です。これを機に、自分の人生の終着点を見直し、より自由で、自分の意思を大切にした未来を考える準備をしてみてはいかがでしょうか。

